| 教授名 | ゼミのテーマ/概要 |
|---|---|
 福田 清明 教授 |
民法の改正点を事例で学ぶ (1)ゼミの最初の数回は、教科書1を輪読する。報告者はレジュメを出す。話しやすいテーマでゼミになれてもらう。 |
 畑 宏樹 教授 |
民事裁判の仕組みを通じて民事法の全体構造を体感しつつ、ワンランク上の法的思考力を身につける。 民事紛争の処理のための制度には様々なものがありますが、なかでも民事訴訟制度は実体法(民法・商法)上の権利を裁判所という公権的な機関を介して確定・実現していくプロセスであり、紛争処理のための中心的な制度といえます。 |

波多江 久美子 教授 |
交通事故のケースを題材として、不法行為に基づく損害賠償請求事件の解決について学ぶ 初回はガイダンスと自己紹介を行います。春学期中は、民事交通賠償問題について考えるための基礎的事項について、各自が調べて発表をします。秋学期では、春学期で学んだ基礎知識をもとに、交通事故の損害賠償請求事件の判決についてグループで発表し、皆で議論をします。 |
 今尾 真 教授 |
民法財産法(総則・物権・債権)における最新重要判例研究 ―判例を読み解き、真の法的思考力を獲得しよう! 2023 年度は、春学期は民法判例百選Ⅰ・Ⅱ〔第 9 版〕(2023 年刊行予定)掲載の重要判例を素材として、総則・物権法総論について、1~2 年次の復習を行う。事件における法的問題を的確に抽出・把握する能力、紛争処理に際しての着眼点、解決策提示のための法的論理の組み立て方(法的思考法)、議論の展開の仕方などの力を養成する。ゼミでは、弁護士・裁判官・検察官・司法書士などの法曹志望者にとどまらず、企業法務・公務員などの広義の法曹を含む、法的知識・思考力をもって社会で活躍できる人材育成を行いたい。特に法科大学院進学・公務員試験・各種国家試験資格を目指す学生および 4 年生の参加も大いに歓迎する。 |
 伊室 亜希子 教授 |
民法判例研究 『民法判例百選 II 債権(第 8 版)』の中から、毎回1~2事件を担当者が報告し、皆で議論する。 |
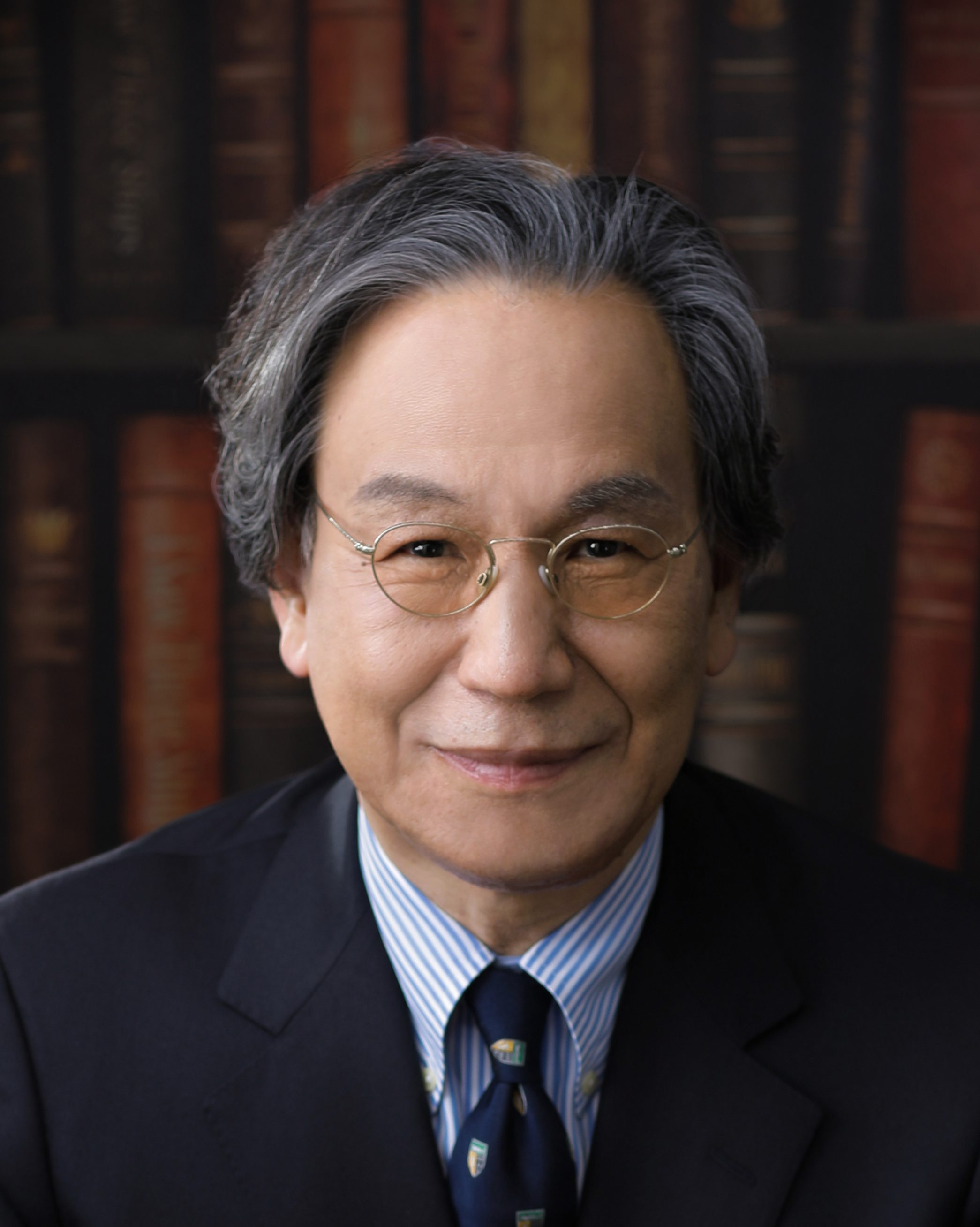 川端 康之 教授 |
租税法の基礎理論 租税法総論を中心に主な論点の判例を分析する |
 小島 秀夫 教授 |
重要判例から学ぶ刑法総論の諸問題 刑法総論の内容について一通り学習した受講生を対象に、刑法総論の重要判例を毎週 1 つずつ扱い、担当者による報告・指定質問・ゼミ生全員による議論を通じて、刑法総論の諸問題を深く検討します。このゼミを通して、知識を習得するだけではなく、法学部出身の社会人に求められる能力、すなわち①広く先例や文献のリサーチを行い、②さまざまな観点から検討を加え、③自分の考えをきちんとした文章でまとめ、④意見を異にする相手に対しても説得力を有する主張を展開し、⑤生産的な意見交換をする能力を身につけていただきたいと思っています。 |
 黒田 美亜紀 教授 |
身近な事例から民法の基本を学ぶ ■本演習では、民法の財産法(総則中心を想定。ゼミ生の希望と必要に応じて物権・債権)および家族法(親族法・相続法)に関する重要基本問題について、判例や事例を素材にして検討し、具体的な問題を法的に解決するための基礎的な能力や方法・バランス感覚を身につけます。 |
 村瀨 健太 専任講師 |
刑事手続における重要論点の検討 ゼミでは、刑事訴訟法に関する諸問題について、報告担当者による報告および受講生のみなさん全員による議論を通じて深く検討します。基本的な進め方としては、毎回、選択したテーマに関する学説や判例および裁判例を調べ、まとめたうえで報告・質疑応答をしてもらいます。ゼミでの報告および質疑応答を通じて、①文献や判例・裁判例等の調査を行い、②対立する考え方について様々な角度から分析を行ったうえで、③自身の見解をまとめ他者に対しても説得的に自身の見解を示すことができる、ということを目指します。 |
 西田 真之 准教授 |
法史学の探求 現在、日本で我々が接する法学は、明治時代に西洋諸外国から学び取った法制度の成果を基本としている。では、過去にはどういう法の世界が広がっていたのだろうか。本ゼミでは法史学をテーマに、現代法との比較の過程で垣間見える「法」の世界の奥深さを探求してゆく。 |
 新津 和典 教授 |
東証プライム上場企業を中心に学ぶ株式会社法の基礎理論 このゼミでは、東証プライム上場企業を中心に具体的な事例を取り上げつつ、株式会社法の基礎理論について勉強しています。詳しくは、法学部ゼミ募集ガイドブックやmanabaにおけるゼミ紹介(「法学部ゼミ募集」より「ゼミ紹介(法律学科)」へアクセス)をご覧下さい。また、このページの一番下に掲載されている「ゼミ生の声」もご覧いただければ幸いです。 |

植田 達 准教授 |
テーマ:労働法の判例研究 このゼミでは、労働法に関する重要な最高裁判例や下級審裁判例を扱います。具体的には、使用者が職場の労働条件を定めた就業規則を労働者にとって不利益に変更することができるのか、使用者が労働者の職種や勤務地を一方的な命令によって変更すること(転勤命令)ができるのか、どのような場合に時間外労働(残業)をさせることが許されるのか、使用者はどのような場合に労働者を解雇することができるのか、使用者のどのような行為が労働者の団結権を侵害する行為(不当労働行為)として禁止されているのか、などの問題を見ていきます。 |
 渡辺 充 教授 |
「市民生活と税金」 1.春学期 |
 山本 未来 准教授 |
行政法研究 本演習では、行政法の理解を深めるために、裁判例を基にした演習や模擬裁判を実施する予定です。また、身近な時事問題についてのディスカッションや実際のパブリックコメント事案への意見提出を行うことにより、行政の諸活動についても広く学んでほしいと思っています。 |
| 教授名 | ゼミのテーマ/概要 |
|---|---|
 穴沢 大輔 教授 |
刑法判例研究 刑法解釈論において重要な判例を素材とし、その分析を通じてそこで何が問題とされているのかを理解し、そのうえで内容について議論してひとつの結論を導くことを目標とする。そこで何を分析するかは、各自の判断(教員が補充・修正等することはあるが)に基づいてまずはなされるので、これまでの講義や生活の中から自分の問題意識を抽出し(選考レポートも参照)、レジュメを作成し、議論に臨んでいただきたい。また、皆でその内容を理解することも重要だと考えている。 |
 福島 成洋 准教授 |
消費者法を手がかりに社会のあり方を考える 社会との結びつきが強いという消費者法の特徴を活かし、消費者法を手がかりとして、社会のあり方について皆で考えてみたいと思います。どういう社会が望ましいのかを考えることは、結局、社会の中で自分はどう生きたいのかを考えることに繋がります。自分の考えを話し、他人の考えに耳を傾けることで、消費者法の理解を深めるとともに、社会や自分自身について深く考える場になればと思っています。 |
 井頭 麻子 准教授 |
環境問題と科学 科学技術は、人類に豊かな暮らしをもたらした一方で、オゾン層破壊や地球温暖化といった地球規模の問題から、光化学スモッグやPM2.5、ゴミ問題、水質汚染といった身近な問題まで、様々な環境問題を引き起こしました。そのような環境問題に漠然とした関心をもっている学生は多いと思いますが、その原因を自分自身でしっかりと調べたことはあるでしょうか。環境問題を直接的に引き起こしているのは化学物質です。その原因物質がどこから発生し、どのように影響を及ぼしているのかを知ることは、環境問題の対策を考える上で必須です。このゼミでは、環境問題を科学的に理解し科学的な思考を身につけるとともに、発表スキルを身につけること、そして今後の生活に役立つような知識を学ぶことを目指します。 |
 来住野 究 教授 |
会社法判例研究 近時の興味深い会社法判例を取り上げ、担当者による報告に基づき、参加者全員で多角的・批判的に討論を行う。報告者はできるだけ多くの文献を渉猟し、レジュメ作成の上、検討内容を詳細に報告することを要し、他のゼミ生も討論での積極的な発言が求められる。ゼミ生が担当した判例につき一生懸命研究したと自負することができ、または会社法全体につき興味が喚起されれば、ゼミの目標の大半は達成されたということができる。また、ゼミを通じて気のおけない友人が作れれば幸いである。 |
 近藤 隆司 教授 |
倒産判例研究 倒産法(破産法、民事再生法、会社更生法など)に関する判例について、ゼミ生による報告と、これに基づく質疑応答・討論を行います。 |
 倉重 八千代 教授 |
民法および消費者法の重要判例研究 ゼミでは、民法および消費者法の比較的新しい平成に入ってからの重要判例・裁判例や、現代社会の複雑化と多様化、消費社会の変容と高度化を背景に起きている新しい法律問題を素材に、実社会では、どのようなトラブルが起こり、これに対して、どのような法的解決方法があるのかを学び、民法および消費者法の理解を深め、リーガルマインドを養うことを目的とします。 |
 宮地 基 教授 |
憲法に関する個別的諸問題の研究 受講者各自が自分の研究テーマを決め、研究の成果を順次授業中に報告して、学年末にゼミ論文にまとめます。多少なりとも憲法に関係があれば、どんな研究テーマを選んでもかまいません。なお、法科大学院進学希望者、公務員試験受験希望者には、教員からそれぞれの進路に適したテーマを提案します。 |

中山 岳洋 助教 |
知的財産法事例研究 教員が、知的財産法に関する事例を依頼者からの相談事例という形式で用意する。参加者において、弁護士や会社の法務部員となったつもりで、相談事例についてどのような知的財産法上の請求等ができるのかを考えてもらい、また、相談事例が裁判にまで発展したと仮定して、原告と被告の立場でそれぞれの主張を検討してもらう。 |

能勢 弘章 准教授 |
消費者政策と消費者法 本ゼミは、消費者政策に関するテーマを各自で設定した上で、そのテーマについて調査し、自分なりの分析を行い、それらをゼミで発表・議論することを内容とします。 春学期においては、担当教員による説明とグループワークに加えて、参加者共通の内容(規制・制度や裁判例)について、個人で分担して調査・発表する機会を設けます。 秋学期においては、自身で設定したテーマについて調査・分析し、ゼミで発表してもらいます。 |
 大木 満 教授 |
民法に関する判例および事例研究 ゼミでは、民法(財産法)の基本問題について、判例および事例問題を素材に検討していきます。判例・事例研究を通じて、民法に関する理解を深めることを目指します。具体的な事実関係に対する法の適用を学ぶことによって法を立体的に勉強し、最終的には民法の基礎知識や運用能力を総合的に身につけることを目的とします。その他に、ゼミ活動を通じて、問題を自分で発見して解決できる能力、資料収集や調査する能力、自分の主張を明快に人に伝えられるプレゼンテーション能力、他者と議論するディベート能力などの向上も、できる限り養っていきたいと思います。 |
 大野 武 教授 |
民法・土地住宅法の研究 2023 年度の演習では、「マンション法」についての考察を行う。 |
 櫻井 成一朗 教授 |
法律と人工知能 現在、AI は第三次ブームを迎え、AI ブームを迎えています。大学においても、AI・データサイエンス教育が開始されており、AI 社会を迎えようとしています。本ゼミでは、「AIと法」をメインテーマに様々な問題に取り組んで行きます。春学期は、古典的人工知能プログラミングにより法律人工知能のプロトタイプ作りを行います。秋学期は、最新のAI技術について学び、AI 社会の様々な問題について様々な観点から皆で検討して参ります。 |
 高橋 順子 准教授 |
ゲームプログラミング研究 本ゼミでは、コンピュータを用いた情報処理技術の応用として、オリジナルなコンピュータゲームの制作を目指します。春学期はC#言語による中級以上のプログラミングができるようになるための基礎演習とゲーム統合開発ツールUnityを用いた実践的なゲーム制作演習を行います。夏休みのゼミ合宿から、コンピュータグラフィックス、カードゲーム、ロールプレイングゲーム、シューティングゲームなどのより高度なプログラミングテクニックについて学び、最終的に応用作品としてオリジナルなコンピュータゲームのプログラムを制作していきます。 |
 鶴貝 達政 教授 |
情報処理研究 コンピュータを使用して情報処理を行うためにはアプリケーションプログラム(例えば、文章を作成するためのワードや表計算のためのエクセルなど)が必要です。アプリケーションプログラムはプログラミング言語(C言語や perl など)で作成しますが、プログラムの基本的な仕組みはたったの5つ((1)出力、(2)計算、(3)入力、(4)条件判定、(5)繰り返し)からできており、この演習ではそれを応用してアプリケーションプログラムの作成を行います。 |
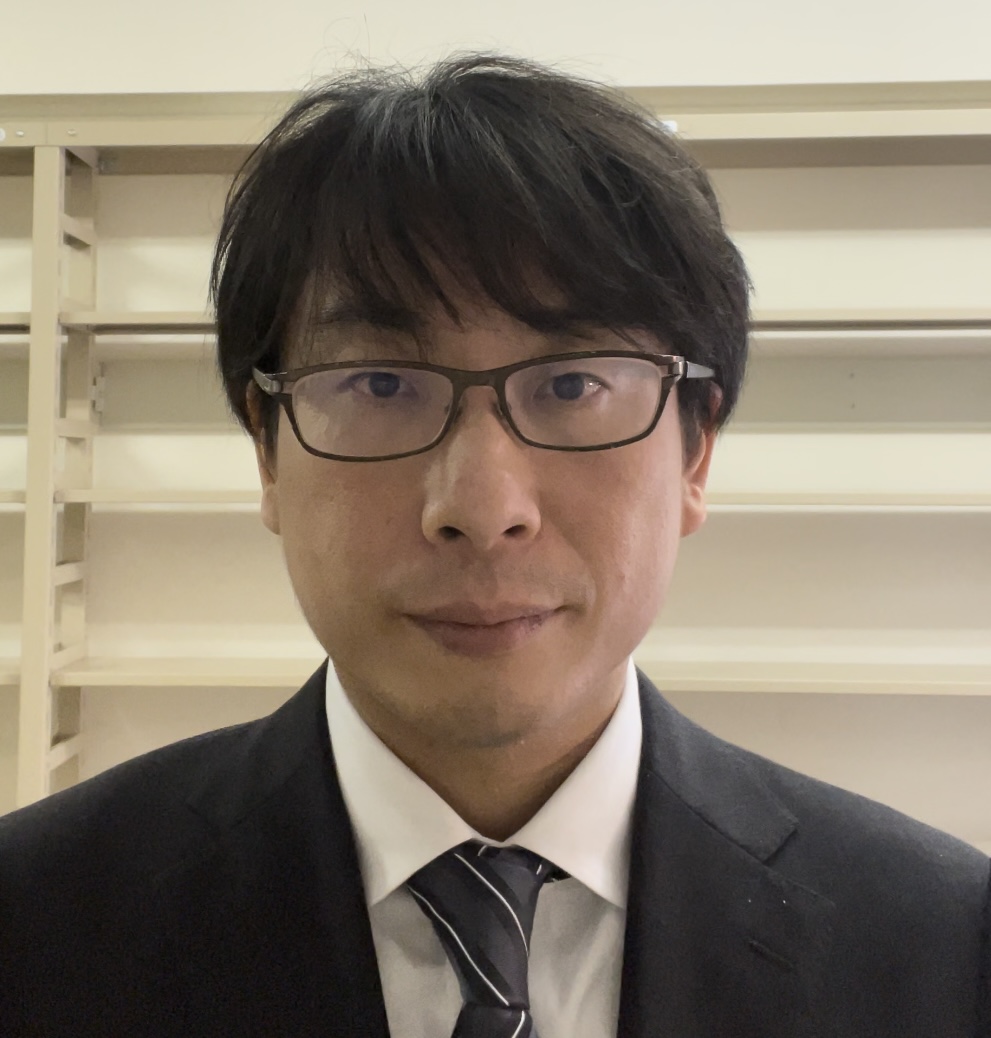 吉田 豊 専任講師 |
プログラミングを通して見る自然科学 プログラミングは人の手で行うには困難なデータの分析や計算を容易にし、物理学など様々な自然科学やデータサイエンスの分野で幅広く用いられています。このゼミの前半ではプログラミング言語 Pythonを通してプログラミングの初歩を学ぶことを目的とします。その後、Pythonを用いて量子コンピュータ、統計学などから話題を選び、プログラミングがどのように自然科学に応用されているかを理解することを目的とします。ゼミの後半では自らプログラムを制作して発表を行なってもらう予定です。 |
| 教授名 | ゼミのテーマ/概要 |
|---|---|
 阿部 満 教授 |
気候変動法・環境法の研究 みなさんは、気候変動の影響や原因について説明できるでしょうか。,さらに、人類が気候変動に対してどのような取り組みをしているのか、その取り組みは私たちの生活、企業活動にどのような影響を及ぼすのか、考えたことがあるでしょうか。気候変動について考えることは、今後の人類のあり方を思考すると言っても過言ではないでしょう。 |
 蛯原 健介 教授 |
比較ワイン法研究室 ~ワインとホップから地域や世界を考える~ ◆このゼミは、日本初、かつ日本唯一(だと思います)の「ワイン法ゼミ」です。学内でのゼミだけではなく、現場での研修を通して、ぶどう栽培、ワイン醸造、ラベル表示、ワインの流通や国際取引にかかわる国内外のルールを学びます。あわせて、社会で通用するプレゼンテーションのスキルやコミュニケーション力を身につけます。秋学期には、各自が選んだテーマについて調査を行い、8000 字程度のリサーチペーパーを執筆します。 |
 東澤 靖 教授 |
国際人権法研究 紛争と難民、ジェンダー、LGBT、ヘイトスピーチなど、国際社会や日本の社会で起きているさまざまな問題を取り上げながら、それらの問題を考えるための国際人権法について研究する。また、ビジネスと人権など、新たな取り組みが始まっている分野も調査する。最初の方で基礎的な知識を学んだ上で、それぞれのテーマを調査し、発表やディスカッションを行う。 |
 三浦 基生 専任講師 |
法哲学研究 法哲学は「法とはなにか?」「法とそれ以外の規範(例えば道徳)はどう関わるか?」「正義とは何か?」といった法の基礎にある概念・価値に関わる根本的な問いを扱います。 |
 小野木 尚 准教授 |
国際取引における交渉および仲裁 このゼミでは、紛争解決方法としての仲裁と交渉について学びます。紛争が生じた際に、裁判や仲裁によって解決を試みる場合には、原則として一方が勝ち、一方が負けるという結果となります(win or lose)。しかし、交渉を試みれば、双方の利益を満たすような解決が可能となるかもしれません(win-win)。このような、裁判(仲裁)と交渉との違いを理解した上で、ロールプレイや模擬仲裁および模擬交渉を通じて、国際取引紛争事例を題材としてさまざまな紛争解決方法を実践的に学びます。将来、国際的な企業法務に携わりたい方などにもぜひ受講してほしいです。 |
 申 美穂 准教授 |
国際私法研究 国際私法とは、国際契約、国際結婚、国際養子縁組のような、国際的な私人間の法律関係について、適用される法律(準拠法)を内国・外国の法律の中から選ぶという特殊な機能を持った法律です(日本では、「法の適用に関する通則法」が主な法源)。「国際私法って初めて聞いたし、自分にはあまり縁がなさそう」と思う人は多いと思いますが、交通手段・通信手段が発達し、外国と関わる機会が飛躍的に増えている今日、国際私法はおそらく、皆さんが思っている以上に身近な法律です(注:国際私法は国際法とは異なります!)。 |
 鶴田 順 准教授 |
国際法研究 さまざまな社会的な問題と向き合った際に、法が問題状況の改善・克服にいかなる役割を果たしているのか・いないのかという関心から調査を進め、分析を行い、自分の考えをまとめ、その成果をひろく社会に発信します。 |

ヴァラー モリー 准教授 |
和歌で見る京都・奈良 In this seminar, we will explore famous places in the waka tradition. We will focus on sites in and around the ancient capitals of Kyoto and Nara, while also examining key points beyond. Why were these places |
| 教授名 | ゼミのテーマ/概要 |
|---|---|
 池本 大輔 教授 |
リベラル国際秩序の行方 東西冷戦後の世界では、欧米諸国を中心に、民主主義・人権・市場経済(グローバル化)・法の支配の諸価値にもとづく、「リベラル国際秩序」を築こうという動きが強まった。しかし最近になって、この「リベラル国際秩序」は、中国・ロシアによる挑戦や先進民主主義諸国におけるポピュリズムの台頭、コロナ感染症の流行という形で、内外からの挑戦にさらされている。わたしたちの住む日本も、そうした潮流の例外ではありえない。そこでこのゼミでは、冷戦後の時代について振り返った上で、今後の世界がどのような方向に向かおうとしているのか、民主主義に未来はあるのか、日本はどのような道を選ぶべきなのか、みんなと一緒に考えてみたい。具体的に取り上げるテーマや文献は、参加学生のアンケートによって決定する。 |
 鍛冶 智也 教授 |
まちづくりの実態と課題(事例研究を通じた意思決定と事業手法の研究) ここ数年は,上記に掲げているテーマを基本として,より具体性のある絞ったトピックでゼミを開催しています。2025年度は「首都圏のニュータウンの更新の課題」(過去には,「全国の地域活性化政策における諸課題」「ワイン産業を通じたまちづくり」「子育てに関わる地域支援活動」「商店街の実態」「国内及び海外の市街地活性化」などの調査研究がある)を調査・研究する予定です。 |
 久保 浩樹 准教授 |
現代世界における議会・政党・選挙 このゼミでは、現代の私たちが生きる社会、とりわけ民主主義的な政治制度の根幹をなす議会制度と選挙制度について世界全体の中での比較という視野から理解を深めることを目的としています。 |
 熊谷 英人 准教授 |
「政治」を読む 熊谷ゼミでは、「政治」にかかわる課題文献を読み、ペーパーを書き、議論します。 |
 葛谷 彩 教授 |
歴史の中で国際関係を考える 昨年に引き続き、本ゼミでは、国際問題について歴史的視点から考えることを目的として、関連図書を講読する。ゼミで行う内容は基本的にゼミ生の関心に即して決まる。原則として新書の場合は毎週1冊、単行本の場合は2週間で1冊のペースで講読する。ゼミ生からの積極的なアプローチがなければ何も進まない。逆にそれがあれば、文献講読の他、ディスカッションやフィールドワーク、外部ゲストの講演なども行うことができる。「求めよ、さらば与えられん」が本ゼミの基本方針である。 |
 溝渕 正季 准教授 |
変革期社会の比較政治社会学 本ゼミでは、主にアジア・アフリカ諸国で頻繁にみられる政治・社会問題について、理論と実証の両面から考えていきます。主権国家として独立してからまだ100年も経過していない、依然として変革期にあるそれらの国々では、欧米諸国とは大きく異なる問題にたびたび出くわします。たとえば、極端に低い武力行使のハードル、頻発する戦争・内戦、頑健な権威主義と自由や民主主義の不在、軍の頻繁な政治介入、ポピュリズムの台頭、宗教の巨大な政治・社会的影響力、腐敗や汚職、経済発展の遅れ、といった問題です。もっとも、こうした問題は、近年、成熟した民主主義体制を備えていると思われた欧米諸国でも次第にみられるようになってきました(その意味で、本ゼミでは、変革期にある社会・国家であれば地域を問わず研究対象とします)。いずれにせよ、ゼミで具体的に取り上げるテーマや文献については、参加学生と相談の上で決定します。 |
 毛 桂榮 教授 |
政府は、国民の「健康」にどこまで責任をもつのか: 煙草とアルコールの政府規制に関する比較研究 キャンバスなど公共施設での喫煙規制が強化されている。飲酒規制も同様。規制は、年齢規制、場所規制、表示規制など様々。各国の規制も多様。このゼミでは、煙草とアルコールを例に各国の規制を調査し、比較研究を行う。例えば生産・輸入・購入・消費(未成年、場所)の規制、広告の規制、パッケージの表示規制などの比較研究。(主として喫煙規制の)健康増進法があるように「健康」がキーワードで、この研究は、煙草とアルコールの規制の比較研究を通じて、政府が国民の健康に責任を有することのあり方などを研究する。 |
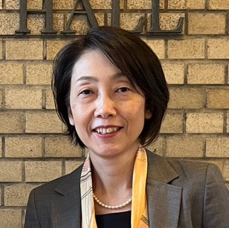 中谷 美穂 教授 |
様々な政治現象・公共政策のあり方に対する「なぜ」に向き合う 本ゼミでは、皆さんが持ち寄る政治現象や公共政策に対する「なぜ」に取り組むためのツール(問題解決手法)を学び、それらの問いに向き合います。特に日本の国・地方レベルの政治過程(有権者の行動・政治家や政党の行動・メディア報道のあり方など)、公共政策のあり方に軸足を置いて研究していきます。 |
 西村 万里子 教授 |
公共政策研究-福祉・環境・まちづくり・雇用等、社会課題の調査研究、 政策提言 ・福祉・環境・まちづくり・教育等の社会課題をとりあげ、理論と実態の両面から調査・研究を行い、政策提言することを目指します。 |
 佐々木 雄一 准教授 |
日本の政治・社会・メディア 日本の政治や社会に関する文献を読み、ペーパーを書き、ディスカッションをします。 |
 渡部 純 教授 |
日本政治の諸問題 本年度は、映像作家岩井俊二の作品を取り上げ、そこに隠された暴力の契機を読み解くことで、1980年代以降の日本社会にある平和観・政治観の特質を新たな角度から明らかにしていきたい。 |



